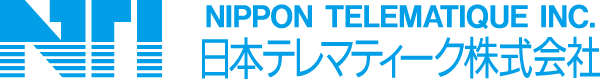この記事でわかること
「対策の必要性はわかっているが、時間も人も足りない…」
そんな状況でも“やれる”仕組みとその具体的な実践方法を解説します。
ひとり情シスが陥る構造的な限界とは
中堅・中小企業において、情報システム部門が1名または兼任という体制は珍しくありません。
IPAの「情報セキュリティ白書2024」では、企業のセキュリティ課題として「人材不足」などが挙げられています。
ひとり情シスの日常業務には以下のような課題が内在しています。
- PCキッティング・ネットワークトラブル・クラウド設定など多岐にわたる対応
- 資産台帳の整備が形骸化し、野良サーバやテスト環境の存在が把握できていない
- CVE(脆弱性情報)を把握しても、影響分析と対処まで手が回らない
- セキュリティチェックシートには形式的に「対策済み」と記載せざるを得ない
これらはすべて、個人のスキルや意識の問題ではなく、業務設計・体制設計の不在による構造的な限界です。
【なぜ今、対策が急務なのか?】
- サプライチェーン攻撃の踏み台化:セキュリティが手薄な中小企業が、取引先である大手企業を攻撃するための「踏み台」にされるケースが増加しています。自社が被害者になるだけでなく、取引先への加害者になるリスクを抱えているのです。
- クラウド設定ミス:DXのために導入したクラウドサービス(IaaS/SaaS)の管理が追いつかず、意図せず情報が外部に公開される設定ミスが後を絶ちません。これが新たな攻撃の侵入口となっています。
従来型診断が機能しにくい理由
外部の専門家による脆弱性診断を導入している企業もありますが、その多くが「実施しただけ」で終わっているのが実態です。
- 優先順位が見えない:CVSSスコアが高い=対応優先とは限らない
- 内容が専門的すぎる:経営層・現場ともに理解・合意形成が困難
- 静的なスナップショット:診断時点での情報が、変化の早い環境で陳腐化
つまり、診断は実施したが、運用設計に落ちていないことで「宝の持ち腐れ」になっているのです。
ASMと自動診断の実効性
こうした問題に対して、近年注目されているのがASM(Attack Surface Management)です。
これは、攻撃者の視点で外部から見たIT資産を継続的に棚卸・可視化する仕組みです。
従来の診断では、「本番環境の範囲内だけ見ていれば安心」と思いがちですが、攻撃者はそう考えてくれません。VPNや開発環境、公開設定ミス、古いSaaS登録など、“外から見える”というだけで狙われる現実があります。
ASMはまさにその“攻撃者の視点”を代替する仕組みであり、「気づけなかった盲点」を日常的に可視化する役割を果たします。
たとえばBreachRiskでは、公開中のWeb資産・VPN・SaaS設定などを自動調査し、impact(影響度)× likelihood(攻撃可能性)でリスクスコア化します。
- 棚卸が「自動で回る」ため、人的リソース不要
- EPSS(Exploit Prediction Scoring System)などの指標で悪用可能性を判断
- リスクはスコアで定量化され、対応優先度が明確
米国ではこの仕組みを保険料に活用する動きもあり、BreachBitsとLloyd’s保険組合が連携した「Risk Collective」では、
「信頼できる第三者評価を導入している企業は保険料を割引」する枠組みが構築されています。
【セキュリティが「コスト」から「投資」へ】
この事例が示しているのは、「適切なセキュリティ対策が、保険料の割引という直接的なリターンを生む投資になる」という新しい潮流です。これは、セキュリティを単なるコストセンターと捉えるのではなく、事業継続性や企業信頼性を高め、さらには金銭的メリットにも繋がる戦略的な投資であると経営層に説明するための強力なロジックになります。
明日からできる「知る→伝える→回す」の3ステップ
Step 1:知る
まずは、無料診断などで「自社が外からどう見えているか」を把握する。
この段階で、不要なサーバや誤設定が見つかるケースも多く、認識とのズレが明確になります。
Step 2:伝える
スコア付きの診断レポートは、経営層への説明にも活用できます。
「感覚」ではなく「定量データ」で示すことで、予算化や優先度設定の説得力が向上します。
Step 3:回す
対応すべき項目を絞って優先対応。週次のスコアレポートで改善推移を追う。
診断と評価が自動化されていれば、対応リソースは「人がやるべき部分」に集中できます。
【見つかったリスクへの具体的な対処法】
- ① パッチ適用:メーカーから提供される修正プログラムを適用する。(基本)
- ② 設定変更:不要なポートを閉じる、アクセス制限を強化するなど、設定でリスクを回避する。
- ③ 仮想パッチ(WAFなど):すぐに修正できないシステムの場合、WAF(Web Application Firewall)などで攻撃を防ぐ暫定対策をとる。
- ④ リスク受容:影響が極めて軽微で、対策コストが見合わない場合、リスクを「受容」するという経営判断も必要。
⚠️ ツールの過信は禁物: ASMツールは「外部から見えるリスク」の発見に非常に強力ですが、万能ではありません。従業員のマルウェア感染といった「内部の脅威」には別途対策が必要です。セキュリティは多層防御が基本であることを忘れないようにしましょう。
まとめ:構造的な「絶望」から、具体的な「希望」へ
この記事の冒頭で、ひとり情シスが直面する、個人の努力ではどうにもならない「構造的な問題」について述べました。
- 多すぎる業務で、セキュリティに割く時間がない…
- そもそも自社のIT資産をすべて把握できていない…
- 大量の脆弱性情報の中から、何を優先すべきかわからない…
- 経営層や他部門にリスクを説明し、協力を得るのが難しい…
こうした壁を前に、無力感を覚えるのは当然のことです。
しかし、本記事で紹介したASM(Attack Surface Management)というアプローチは、これらの課題一つひとつに、具体的な処方箋を提示します。
【課題への具体的なアンサー】
- 「時間がない」問題には → 『自動化』で対抗。24時間365日、ツールがリスクを監視してくれます。
- 「把握できない」問題には → 『自動棚卸』で対抗。攻撃者目線で、忘れられた資産も発見します。
- 「わからない」問題には → 『優先順位付け』で対抗。「本当に危険なもの」をスコアで明確に示します。
- 「説得できない」問題には → 『客観的レポート』で対抗。データに基づいた説明で、関係者を動かします。たとえば「この脆弱性はEPSSスコアで97%、現時点で最も攻撃されやすい」と示せば、経営層も対策の必要性を具体的に認識できます。
完璧なセキュリティを目指す必要はありません。重要なのは、賢くツールを活用し、限られたリソースを「本当にやるべきこと」に集中させることです。
「うちは狙われない」と思っていても、攻撃者は“規模”ではなく“攻めやすさ”で自動的に標的を選びます。逆に言えば、「見えている範囲」を絞るだけでも、攻撃リスクは大きく減らせるのです。
まずは無料診断で「自社が外からどう見えているかを知る」という、たった一つのアクションから始めてみませんか。その一歩が、構造的な無力感を打ち破り、主体的なセキュリティ運用への扉を開くはずです。
▶ 無料診断はこちら
※記載された社名・製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。