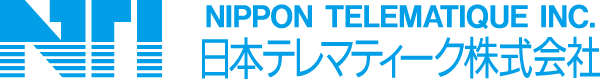この記事でわかること
本記事では、多くの企業が直面するSASE運用の課題を分析し、その解決策として「ブラウザ中心」の新しいセキュリティアプローチを具体的な製品と共に解説します。
SASE運用が課題を生む背景:複雑化するアーキテクチャの罠
「特定のWebサイトにアクセスできない」「クラウドサービスの動作が不安定だ」
情報システム部門には、日々このような問い合わせが数多く寄せられます。特に、セキュリティとネットワーク機能を統合したSASE(Secure Access Service Edge)を導入後、かえってこうした問い合わせ対応が増加し、運用負荷の増大に悩まれているケースは少なくありません。
セキュリティレベルの向上という本来の目的とは裏腹に、現場の担当者様は、終わりの見えないトラブルシューティングに追われているのが実情ではないでしょうか。本記事では、多くの企業が直面する「SASE運用の課題」を乗り越えるための、新しい視点と具体的な解決策を提示します。
なぜ、SASEの運用はこれほどまでに複雑化し、現場の負担を増大させてしまうのでしょうか。その根源には、多くの企業がゼロトラストセキュリティへ移行する過程で直面する「理想と現実のギャップ」が存在します。
クラウドシフトとリモートワークの普及により、従来の境界型防御モデルが有効でなくなったことは、共通の認識です。その解決策としてSASEが登場しましたが、多くの導入プロジェクトは、既存の複雑なネットワークやセキュリティ製品群の上に、新たな機能を重ねていく形になりがちです。
結果として、SWG、CASB、ZTNAなど、様々なベンダーのソリューションが連携する複雑なアーキテクチャが誕生します。それぞれが独自のポリシーとログ体系を持つため、一つの設定変更が意図しない影響を及ぼし、事業部門から「業務ができない」というクレームを引き起こす原因となります。特に、取引先が利用するシステムが独自証明書を利用している場合など、SSLインスペクションが原因で通信が遮断されるといった問題は、典型的な例として挙げられます。
事業部門からの「利便性」の要求と、経営層からの「セキュリティ強化」の要求。その間で、情報システム部門は膨大なログの分析と問い合わせ対応に時間を費やし、本来注力すべき戦略的なIT投資やDX推進といった業務への着手が困難になるという、構造的な課題を抱えているのです。
従来対策の限界:後追いのブラックリストでは巧妙化する攻撃に対応できない現実
こうした複雑な運用を乗り越えてSASEを導入したとしても、現代のサイバー攻撃に対して、万全な対策とは言えなくなってきています。
今日のWebセキュリティにおいて、依然として重要な役割を担っているのは、危険なWebサイトの情報を集約したRBL(Reputation Blacklist)です。しかし、サイバー攻撃、とりわけフィッシング攻撃の巧妙化と高速化は、RBLによる後追い型の対策の限界を露呈させています。
攻撃者は、「Phishing as a Service(サービスとしてのフィッシング)」といったエコシステムを活用し、わずか数日でフィッシングサイトを構築・破棄するサイクルを繰り返します。さらに、生成AIの悪用により、極めて自然で巧妙な日本語の偽装メールが作成され、人間の心理的な隙を突く攻撃が増加しています。IPA(情報処理推進機構)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2025」においても、「フィッシングによる個人情報等の詐取」は極めて深刻な脅威として位置づけられており、この傾向は2026年以降も継続することが強く懸念されます。
後追い対策の限界
昨日まで安全とされていたWebサイトが、今日には攻撃の踏み台になっているかもしれません。既知の脅威リストに依存する対策だけでは、進化し続ける攻撃から組織を守りきることは、極めて困難になっているのです。
発想の転換:セキュリティの重心を「浄水場」から「蛇口」へ
複雑なアーキテクチャ、終わらない問い合わせ対応、そして巧妙化するサイバー攻撃。これらの課題を解決するためには、セキュリティに対する根本的な発想の転換が求められます。
ここで、水の安全を例に考えてみましょう。従来の大規模なセキュリティ対策は、いわば「巨大な浄水場」のようなものです。浄水場では、ダムから送られてくる水を一括でろ過・殺菌し、広域に供給します。SASEがネットワークの出入口ですべての通信を検査するアプローチは、これによく似ています。
しかし、この方法には限界があります。どれだけ浄水場で水をきれいにしても、各家庭に届くまでの長い水道管が老朽化していれば、そこで水が汚染されるリスクは残ります。同様に、SASEで通信を検査しても、ユーザーのエンドポイントに届くまでの間に、新たな脅威が生まれる、あるいは検知をすり抜ける可能性はゼロではありません。
そこで新しいアプローチとして注目されるのが、いわば「蛇口に取り付ける高性能浄水器」という考え方です。ユーザーが水を飲む直前に、蛇口で最終的な安全性を確保する。これと同じように、セキュリティの重心をネットワークの経路上から、ユーザーがWebサイトにアクセスする最終接点である「ブラウザ」へとシフトさせるのです。このアプローチは、ユーザー体験を損なうことなく、より確実な安全を提供できる可能性を秘めています。
新しい解決策の具体化:AIが未知の脅威を判断する「ConcealBrowse」
この「蛇口の高性能浄水器」という新しいアプローチを具現化するのが、次世代セキュアブラウザ「ConcealBrowse」です。ConcealBrowseは、既存のブラウザ(Chrome、Edgeなど)に拡張機能として導入するだけで、ブラウザ自体をインテリジェントなセキュリティセンサーへと進化させます。
最大の特徴は、独自のAIエンジンによるリアルタイムの脅威分析能力です。蛇口の浄水器が、水を飲む直前にAIセンサーで水質を瞬時に分析するように、ユーザーがURLをクリックした瞬間、ConcealBrowseのAIエンジンがWebサイトのあらゆる要素(ドメインの来歴、IPアドレスの評価、サイトの構造、スクリプトの挙動など)を複合的に分析し、リスクを判定します。そして、少しでも疑わしい要素が検知された場合、エンドポイントから完全に隔離された安全な環境でWebサイトを描画(アイソレーション技術)するため、デバイスがマルウェアに感染するリスクを未然に防ぎます。
これは、既知の脅威リストに依存する従来の手法とは一線を画すアプローチです。事実として、ConcealBrowseは、他のセキュリティベンダーがまだ検知していない未知の脅威を、リアルタイムで特定・ブロックした実績が多数報告されています。
例えば、一見すると無害なURLをクリックすると、最終的に多くの人が知るポータルサイト「Yahoo!」のページが表示される、という事例がありました。しかしその裏では、ユーザーに気づかれないように複数のサードパーティサイトを経由し、悪意のあるスクリプトを読み込ませるという巧妙な手口が使われていたのです。ConcealBrowseは、こうした一見しただけでは見抜けない脅威の「挙動」をリアルタイムで分析し、他のベンダーが検知する前にユーザーを保護しました。
この「リアルタイム検知と防御」の能力が、情報システム部門を「問い合わせ祭り」から解放する鍵となります。危険なサイトはインシデント発生前に自動で無害化されるため、アラート対応や事後調査といった運用負荷を大幅に削減することが期待できます。
ConcealBrowseは、既存のSASEやEDRといったセキュリティ投資を置き換えるものではありません。むしろ、それらのソリューションと共存し、防御が手薄になりがちな「ブラウザ」という最後の接点を保護することで、組織の多層防御体制をより一層強固なものにします。
まとめ:煩雑な運用から解放され、戦略的な情報システム部門へ
本記事でご紹介したConcealBrowseは、SASE運用に課題を抱える情報システム部門にとって、まさに「蛇口の高性能浄水器」のような存在となり得ます。
「Webサイトが見られない」といった問い合わせは、危険なサイトが未然にブロックされることで減少し、「ネットワークが遅い」といったクレームは、通信経路に負荷をかけないブラウザベースのアーキテクチャによって解消されるでしょう。
これまで問い合わせ対応に費やしてきた時間は、DXの推進やIT戦略の策定といった、企業価値の向上に直結する、より創造的で戦略的な業務へと振り向けることが可能になるはずです。
現在のセキュリティ運用に限界を感じていらっしゃるのであれば、一度、「ブラウザから始める」という新しいアプローチをご検討されてはいかがでしょうか。それこそが、複雑化した課題を解決に導く、最もシンプルかつ効果的な一歩となるかもしれません。
※記載された社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または商標登録です。